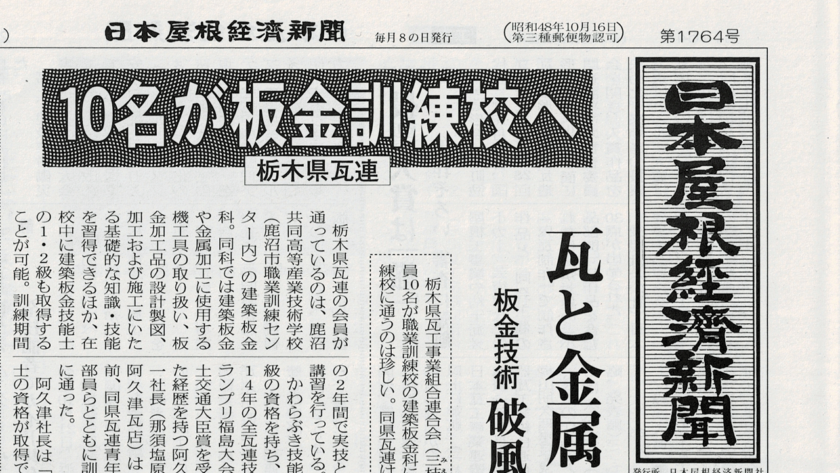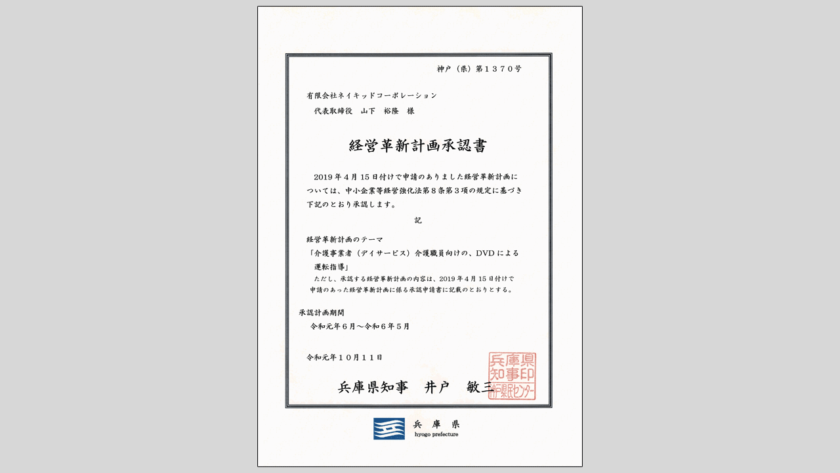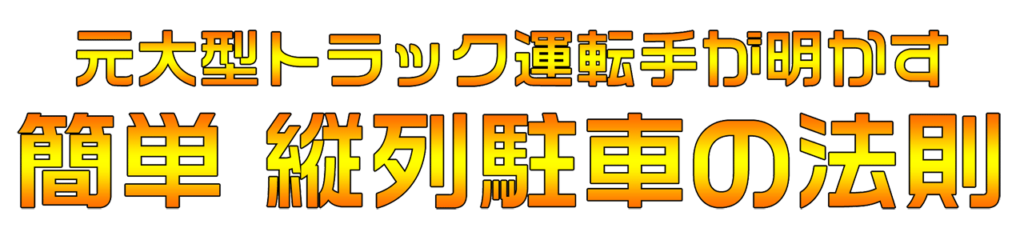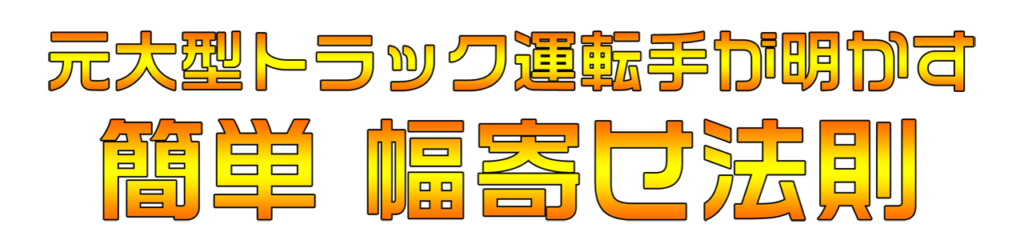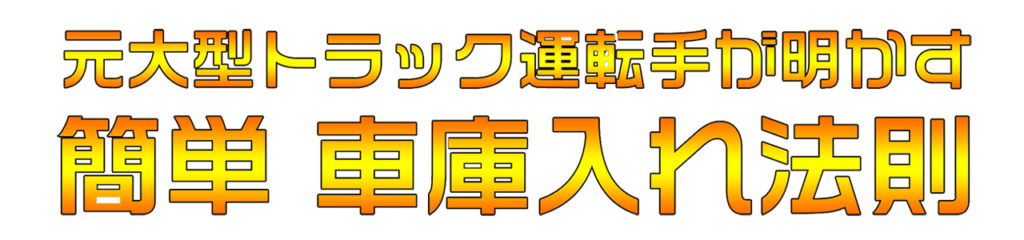ダイハツ工業の福祉介護・共同送迎サービス「ゴイッショ」を採用されている香川県三豊市 社会福祉協議会のドライバーに対して動画を使った運転指導「クルマの運転通信教育」を行ってまいりました。
今日までの運転教育では車を使用して運転練習しなければならないと思われていましたが、車は軽自動車から大型トラックまで車の大きさ・形状などが変わっても絶対に変わることのない、同一の法則(車の原理原則)に基づいて動いています。
この講習会では、最初に屋内で動画閲覧してもらった後に、実際に車を使って動画で解説したように車が動いていることを体験して頂いているシーンとなります。

このイベントには大手損害保険会社の担当者数名も見学に来られ、動画閲覧した損害保険会社の女性社員が写真の車を使って数センチの隙間から車を接触させずに運転することができました。
※ワンボックスカーは生まれて初めて運転されたそうです。

車の大きさ・形状、そしてハンドルの位置(左右)に関係なく、全ての車は同じ法則に基づいて動いているのです。